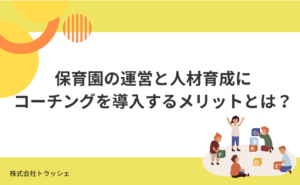組織のゴールを統一する重要性とは?保育園運営に必要な考え方と実践方法
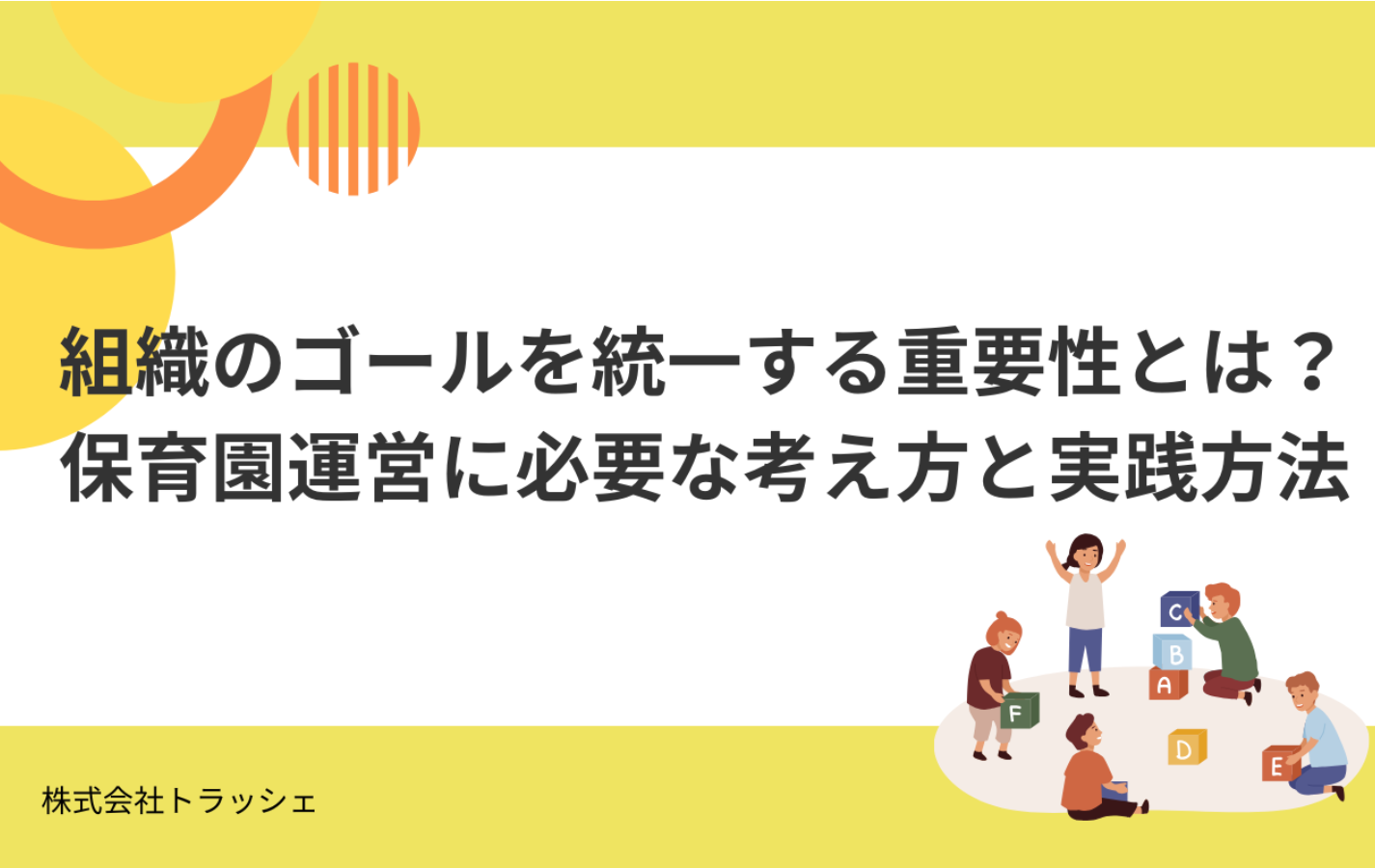
保育園の運営において、組織の目標や方向性を明確にすることは非常に重要です。
現代の保育業界は、待機児童問題や職員の定着率低下、行政方針の変化など、さまざまな課題に直面しています。
その中で、組織全体のゴールを統一することは、保育園運営を円滑にし、スタッフが一丸となって目指すべき方向を明確にするために欠かせません。当記事では、保育園運営におけるゴール設定の重要性とその実践的な考え方について解説します。
保育園を取り巻く現状と課題

日本の保育業界は、多くの家庭にとって欠かせない存在でありながら、いまだにさまざまな課題を抱えています。
これらの課題を理解することは、保育園の運営や政策立案におけるゴール設定を考える上で非常に重要です。
まずは、保育業界の現状を整理し、抱える課題について掘り下げて考察していきましょう。
待機児童問題
待機児童問題は依然として日本の保育業界における大きな課題です。
子ども家庭庁の調査によると、2024年度4月の待機児童数は、2567人と報告されており、約87.5%の市区町村では待機児童なしという結果です。
待機児童数が最も多かった2017年の26018人と比較すれば、その数は大幅に減少しています。このような結果から見ると、待機児童問題は収束に向かっているように見えるかもしれません。
しかし、一部の自治体では依然として待機児童問題は解消されていないという事実があります。中には、100人以上の待機児童が存在する自治体もあります。
| 【待機児童問題の原因】 ・保育施設の不足 ・保育士の不足 ・地域格差 ・保育施設の運営コストの負担 |
また、統計上には含まれないものの、実際には保育を必要としている「隠れ待機児童」の存在も注視しなければなりません。
希望の保育園に入れなかったことで認可保育所以外の施設を利用せざるを得ない家庭、育児休業を延長している家庭は、一定数存在しています。また、その数の把握は困難であるとも言われています。
これらのことを鑑みると、待機児童問題が収束に向かっているとは言い切れないでしょう。
職員の定着率低下
職員の定着率の低下も保育園運営における深刻な問題です。
厚生労働省が発表したデータによると、2019年時点で保育士の離職率は9.3%です。全国の平均離職率は15.6%であることと比べると、離職率は低いという結果になっています。
しかし、ここで注目すべきなのは、勤務する保育士の経験年数です。
経験年数別の割合を見ると、経験年数2年未満が15.5%、2~4年未満が13.3%、4~6年未満が11.1%という結果です。合計すると49.4%ですから、全体の約半数は経験年数6年未満の保育士であることが分かります。
離職率は低いとはいえ、定着率が十分とは言えないのが実情です。
公的なデータではありませんが、新卒保育士の約半数が3年以内に離職しているという結果もあるようです。
| 【離職の主な理由】 ・身体的/精神的負担の大きさ ・賃金水準の低さ ・キャリアパスの不明確さ ・保護者対応の難しさ ・労働環境への不満 |
実際、職員が定着しないことで人手不足が慢性化し、子どもたちに十分なケアを提供することが難しくなる悪循環が生じている園は少なくありません。
保護者からの不安感や採用コストの増加など、さまざまな悪影響もあるでしょう。
また、保育士資格を有していても現場で働くことはしない「潜在保育士」の存在も問題視されることがあります。離職した保育士が復職しないケースも多いのです。
これには、以前の職場での過酷な労働環境や人間関係のトラウマが、復職への大きな心理的障壁となっていると言われることがあります。
離職・復職のどちらにおいても、保育士が抱える不安や懸念に寄り添った包括的な支援が欠かせない要素でしょう。
行政方針の変化
行政方針の変化も保育園の運営に大きな影響を及ぼしています。
子ども・子育て支援新制度の導入以降、規制緩和や補助金制度の変更によって運営資金や施設基準が大きく変化し、保育園は柔軟な対応が求められています。
特に、2017年に導入された「保育士等キャリアアップ研修制度」や「処遇改善等加算Ⅱ」の創設などは、保育園の運営体制そのものの見直しを迫るものとなり、対応に苦慮した保育園も多かったはずです。
| 【行政方針の変化の例】・保育の質の確保・向上への要求 ・職員配置基準の厳格化 ・保育所運営費補助金制度の変更 ・新たな保育ニーズへの対応要請 |
行政による規制や要求水準は年々高まっており、保育園の経営層には迅速かつ適切な判断が求められています。
また、2023年のこども家庭庁の設置を機に、さらなる制度の見直しや改革が予想されます。
変化に対応するための中長期的な経営戦略の策定や、職員の育成計画の立案など、経営管理の重要性は増すでしょう。
行政方針の変化に適切に対応し、質の高い保育サービスを持続的に提供していくためには、経営層の専門性向上と現場スタッフとの密接な連携が欠かせません。
行政の動向を注視しながら、柔軟な運営体制を整えていくことが重要です。
なぜ組織でゴールを設定することが重要なのか

効果的な運営を続けるために不可欠といえるのが、ゴール設定です。
さまざまな課題を抱える保育園運営においては、ゴール設定が特に重要です。
ここでは、組織でゴールを設定する必要性について解説します。
方向性を明確にするため
組織全体で統一されたゴールは、全職員が共通の目的に向かって協力し、効果的に業務を進めるための基盤です。
統一されたゴールを設定することで、以下の効果が期待できるでしょう。
| ・日々の業務における優先順位の明確化 目標に基づいて業務を進めることで、どの業務が最も重要であり、どの業務を後回しにすべきかが自然と明確になります。効率的な業務遂行が可能となります。 ・個々の職員の役割と責任の明確化 統一されたゴールを全職員が理解し、各自の役割が明確に認識されることで、無駄な重複作業や混乱を防ぎます。それぞれが自分の役割に集中し、チーム全体の成果を最大化することができます。 ・中長期的な園の発展方向の共有 単なる日々の運営だけでなく、園の未来を見据えた発展方向を全職員で共有することが重要です。 |
こうすることで、短期的な業務だけでなく、将来的な方向性に沿った計画とアクションが取れるようになります。
ゴールが明確であれば、経営陣から現場の職員に至るまで、各々が自分の役割や責任を意識し、組織の目標に向かって努力できます。
迷いや混乱を防ぐことができるため、職員は何を優先すべきかを理解しやすくなり、組織としての一貫性が保たれるのです。
リソースを最大化するため
限られた人員や予算を最大限に活用するためには、明確なゴール設定が不可欠です。
明確なゴールを設定することで、次のような成果が得られます。
| ・人材育成の焦点の明確化 ゴールに基づき、人材育成にどの分野を重視すべきかが明確になります。これにより、職員のスキルアップや成長に最適なリソースを注ぐことができ、組織全体の能力を高めることができます。 ・設備投資の優先順位付け ゴールに沿った形で、必要な設備や施設の改善、更新の優先順位を決定することができます。これにより、限られた予算を効率的に活用し、施設の質を向上させることができます。 ・業務効率化の方向性の決定 明確なゴールに基づいて業務の効率化を進める方向性を決定することができます。例えば、どのプロセスを自動化するべきか、どの業務を外部に委託するべきか、などが明確になります。 |
ゴールを掲げることで、リソースを有効に活用する道筋が見えてきます。
どのリソースに優先的に投資すべきかを理解し、限られた時間や予算を効率的に配分することができます。
市場の変化に対応するため
保育業界は、待機児童問題や職員不足、社会的な変化など多くの外部要因に影響されやすい業界です。
このような市場の変化に柔軟に対応するためには、組織全体で迅速に行動できる基盤を作ることが求められます。
| ・保護者ニーズの変化への対応 保護者のニーズや価値観は日々変化しています。ゴール設定を行うことで、保護者の期待に応えられるサービスの方向性を明確にし、ニーズの変化に柔軟に対応するための戦略を立てることができます。 ・地域社会との連携強化 地域社会のニーズや社会的な問題に対応するためには、地域との連携が不可欠です。組織全体で目指すべきゴールを共有することで、地域との協力体制を強化し、保育サービスの質を高めることができます。 ・新しい保育サービスの開発 市場のニーズに合わせて新しい保育サービスを開発することが、競争力を維持する鍵となります。ゴール設定を行い、どのような新サービスを提供すべきかを明確にすることで、市場の変化に適応する準備を整えることができます。 |
ゴール設定は、保育業界における変化への適応力を高め、組織全体が一丸となって柔軟に対応できるようになるための重要な手段です。
市場の変化に柔軟に対応するためには、組織全体で迅速に行動できる基盤を作る必要があります。
ゴール設定を通じて、変化に対して適切に対応できるよう、組織全体が統一された方向を持つことが重要です。
組織のゴール設定を難しくする「人・市場・組織」の関係
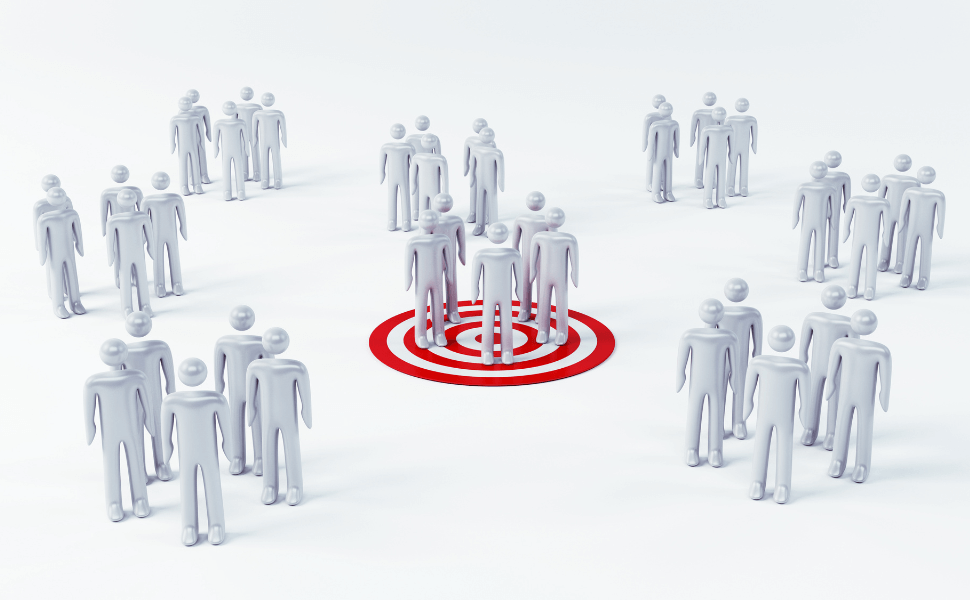
保育業界におけるゴール設定には、「人・市場・組織」の関係性という複雑な要素が絡んでいます。
組織におけるゴールは全体で統一された方向性を持つために設定されるものですが、「人・市場・組織」の関係性によって、ゴール設定が困難になるケースがあるのです。
ここからは、ゴール設定を難しくする「人・市場・組織」の関係について、詳しくみていきましょう。
人は「変わりたくない」を選択する
組織を形成するのは職員です。
そのため、組織のゴール設定においては、職員一人ひとりの心理的な課題を理解しなければなりません。
人間は本能的な傾向として、変化を避け現状維持を選ぶことがあります。
この「現状維持バイアス」は、私たちが日常生活で繰り返し行う行動や決定に強い影響を与え、変化に対する抵抗を生じさせます。
特に新しいゴールを設定する際には、その先にある不確実性や未知の領域に対する不安から抵抗感が強くなることが多いです。
人が変化に対して抵抗を示すのは、心理的な安心感を求めるからです。
この心理に大きく作用するものに、「コンフォートゾーン(快適領域)」があります。
| 【コンフォートゾーンとは】 コンフォートゾーンは、人が最も安心できる環境を指します。この範囲内では、予測可能な状況に囲まれ、リスクを避けることができるため、安心感を得ることができます。しかし、同時にこのゾーンに留まり続けることは、自己成長や新たな挑戦の機会を失うことにも繋がります。コンフォートゾーンは、個人や組織が最も安心感を得られる、慣れ親しんだ行動や考え方の範囲を指します。このゾーンにいると、目の前にある問題に対して直面することなく、無理なく日々を過ごすことができます。しかし、このコンフォートゾーンに留まり続けることには、次第に成長の限界が訪れるという欠点もあります。 |
人間の「変わりたくない」という意識やコンフォートゾーンで感じる安心感は、以下のような現象で変化に対する抵抗を生むことがあります。
| ・既存の業務手順への固執 組織内で「これまでうまくいった方法」があると、職員やリーダーはその方法に対する信頼感を持ち続け、変化への抵抗を感じます。新しい手法やツールが提案されても、既存の手順に慣れているため、リスクを冒したくないという気持ちから、変化を受け入れにくくなるのです。ミスやトラブルに対する恐れから、慣れ親しんだ手順に固執するケースも少なくありません。 ・新しい取り組みへの抵抗 保育業界では、子どもたちの安全や成長に直接関わる業務が多いため、変更に対して敏感です。新しい教育方針や保育手法が導入される際、保育士は「今まで通りでいい」と考え、変化に対して消極的になることがあります。こうした抵抗は決して否定的な姿勢ではなく、むしろ現場での慎重な判断や子どもたちへの思い入れが表れているとも言えるでしょう。 ・成功体験への過度な依存 以前にうまくいった方法や取り組みがあると、それに依存してしまいがちです。過去の成功体験が強く影響し、それを繰り返せば安定すると感じるため、新しい方法を取り入れることへの抵抗感が強くなるのです。特に、業界においては「これまでうまくやってきた」ことに固執し、新しいアプローチへの不安を抱くことがあります。 |
新たな目標を掲げることだけが、ゴール設定ではありません。
過去の事例を活かしつつ、子どもの安全を最優先に、現状のやり方や考え方を見直すことが出発点です。
個人の不安や抵抗感、思い込みに左右されるものではなく、設定したゴールが現場や子どもたちに与えるメリットが明確であるかが、最も重要ではないでしょうか。
市場は「変わる」を繰り返す
特に保育現場のような高い責任が求められる業界では、既存の方法や業務手順に固執する傾向が強く見られます。
しかし、保育業界は急速に変化しているため、これに対応することは組織にとって重要な課題です。
保育市場の変化には、働き方改革やテクノロジーの進歩、保護者の価値観の多様化など、さまざまな要因が影響しています。
| ・働き方改革による保育ニーズの変化 働き方改革は、保育業界に新たなニーズを生んでいます。共働き家庭が増え、長時間の保育や柔軟な勤務時間に対応するための仕組みが求められるようになりました。また、保育士自身の働き方やワークライフバランスも注目され、業務効率化や働きやすい環境作りが急務となっています。これに対応するためには、保育施設の運営体制や職員のトレーニング、シフト制度の見直しが必要です。 ・テクノロジーの進歩による保育環境の変化 テクノロジーの進歩は、保育の現場にも革新をもたらしています。タブレットやスマートフォンを活用した保育日誌やコミュニケーションツールが普及し、保護者との情報共有が迅速かつ効率的になりました。また、AIやIoT技術を活用した安全管理や健康管理のシステムが導入され、保育環境はますますデジタル化しています。こうした技術を活用することで、保育士の業務負担軽減や、保護者の安心感を高めることが可能になります。 ・保護者の価値観の多様化 現代の保護者は、従来の保育サービスに対して高い期待を持っています。教育的な価値観が多様化する中で、保護者は単に「預ける」ことに留まらず、子どもの成長や発達に対して積極的に関わりたいと考えています。また、保育施設の選定基準も、単なる立地や料金だけでなく、施設の教育方針や環境、スタッフの質などが重視されています。このため、保育園や施設は、保護者の多様な価値観に応える形でサービスの質を向上させる必要があります。 |
保育園運営において、これらの変化を無視することはできません。
急速な環境の変化は、組織のゴール設定を難しくし、時には惑わす要因となることもあります。
先述した、コンフォートゾーンから大きく踏み出すことを求められる局面も増えています。
変わるべき要素と維持すべき要素の見極めは、適切なゴール設定に不可欠な要素といえるでしょう。
組織は「変わらない」と衰退する
「変わりたくない」人と「変わり続ける」市場。
この両極ともいえる状況のなかで、組織はどうあるべきなのでしょうか。
市場の急速な変化に対応しない組織は、競争力を失い、最終的には衰退する危険性があることは明白です。
それは保育業界でも同様に言えることです。
変化を避けることは、一時的に安心感をもたらすかもしれません。表向きは、考え得るリスクを避けるための最善策に見えることもあるでしょう。
ただし、ゴール設定をするうえでは長期的な視点を持ち、何が本当のリスクであるかを見極める必要があるのです。
| ・サービス品質の低下 時代に合わない方法やサービスを続けることは、品質の低下を招きます。たとえば、テクノロジーの導入が遅れると、情報管理や保護者とのコミュニケーションが煩雑になり、サービスのスムーズさや質が低下するなどです。また、保育士の業務負担が増加し、集中力や注意力が低下すれば、保育の質にも影響が出ます。保育の質が低下したことで保護者からの信頼を失うことが、長期的な事業の存続に大きなリスクをもたらす場合もあります。 ・職員のモチベーション低下 組織が変化を拒むことで、職員のモチベーションは次第に低下します。新しい取り組みや改善がない環境では、職員が日々の仕事に対して新たな意欲を持つことは難しくなります。特に保育士は、教育の質や子どもたちの成長に対して強い責任感を持っているため、労働環境やキャリアの成長機会がない場合、離職の原因になることもあります。組織が進化していないと感じる職員は、他の施設や業界に転職を検討する可能性も高まります。 ・競争力の喪失 保育業界は競争が激化しており、他の施設との差別化が重要です。市場のニーズや技術の進化に対応しない施設は、次第に他の施設に遅れを取ります。サービス内容や施設の魅力が乏しくなると、保護者からの選ばれる機会が減少し、競争力が喪失します。最終的には、施設の経営が厳しくなり、事業継続が困難になることもあるでしょう。 |
組織が市場の変化に適応できるかどうかは、その後の成長や競争力に大きな影響を与える要素です。
変化し続ける市場を受け入れて柔軟に対応することが、組織、ひいては企業の根本的な使命である「利益の最大化」を実現するためには必要でしょう。
組織のゴールをコンフォートゾーンの外に設定すべき理由

子どもたちの安全や健やかな成長を最優先にする保育現場では、業務が定型化しやすく、新しい方法や革新を取り入れることへの抵抗感が生じることがあります。
変わらなければならないと理解しつつも、変化を拒むケースは少なくありません。
もちろん、子どもの安全や成長が最優先であることは間違いありません。
しかし、現状維持に固執することで、保育の質や対応力を低下させるリスクを伴う場合があるのは事実です。
変化を拒むことは、必ずしも子どもたちにとって最善ではないこともあるでしょう。
特にゴール設定においては、現状に甘んじるのではなく、コンフォートゾーンを超えて新たな挑戦を受け入れることが重要です。
ここからは、なぜコンフォートゾーンを超え、変化を受け入れるべきなのか、その理由を具体的に見ていきましょう。
職員の成長が促進される
職員が現状に甘んじることなく新たな挑戦を続けることで、自己成長が加速します。
たとえば、オンライン研修プログラムへの参加で、新しい保育スキルを習得するなどです。
個人の専門性向上だけでなく、その知識や経験が組織内で共有されることで、園全体の保育の質の向上にもつながります。
また、挑戦的な目標に向かって努力する過程では、職員間の協力体制が強化され、チームワークの向上も期待できるでしょう。
革新的な組織文化が生まれる
新たなゴールは、従来の方法にとらわれない柔軟で創造的なアイデアを生むきっかけとなります。
具体的には、ICTツールの導入により業務効率化を図る、他業界のマネジメント手法を保育現場に応用するなどです。
さまざまな取り組みを可能にすることで、革新的な文化が醸成されます。
若手職員の意見も積極的に取り入れる環境を作ることで、世代を超えた活発な意見交換が促進されるでしょう。
<h3>外部評価の向上</h3>
変化に対する積極的な取り組みは、保護者や地域社会、行政機関からの信頼を高める重要な要素となります。
たとえば、保育の様子をデジタル記録で日々共有したり、地域の子育て支援イベントを主催したりして、園の存在価値や専門性をアピールするなどです。
第三者評価で高評価につながれば、選ばれる園としてのブランド力向上が期待できるでしょう。
経営の多様性と可能性を広げる
新しい挑戦を通じて、思いもよらない事業機会や連携先を発見できることがあります。
企業やNPO、研究機関との協働により、先進的な保育プログラムの開発や、助成金・補助金の獲得機会が増えるなど、経営基盤の強化につながることも考えられます。
さらに、多様な連携経験は、将来の事業展開におけるヒントや可能性を広げることにもなるでしょう。
組織でゴールを共有するための具体的なステップ

組織のゴールは、単に設定するだけでは役割を果たしません。
最も重要なのは、組織でゴールを共有することです。
ここでは、組織でゴールを共有するための具体的なステップについて解説します。
現状の課題を洗い出す
まずは、保育園が直面している課題を明確にします。職員の意見やデータをもとに、改善すべき点を整理しましょう。
このプロセスでは、以下のような多角的なアプローチが効果的です。
| アプローチ方法 | |
| 職員アンケートの実施 | ・現場の声を数値化・可視化・匿名性を確保し、率直な意見を収集・部署や経験年数別の分析 |
| データに基づく分析 | ・残業時間の推移・保護者からのフィードバック・園児の発達記録・業務効率の測定 |
| 外部評価の活用 | ・第三者評価の結果・保護者満足度調査・地域からの評価 |
ゴールを明確にする
課題解決に向けた大きなゴールを設定する場合には、具体性と実現可能性を考慮することが重要です。
ゴールの設定には、以下のSMART原則に基づいて検討するのが有効です。
| SMART原則 | |
| Specific(具体的) | ・具体的な目標を設定する 例:「業務効率を上げる」ではなく「記録作業時間を30%削減する」 |
| Measurable(測定可能) | ・数値目標を設定し、進捗を可視化 |
| Achievable(達成可能) | ・現状の資源と能力で実現できる範囲 |
| Relevant(関連性) | ・園の理念や方針との整合性 |
| Time-bound(期限付き) | ・実現までの時間軸を明確に |
具体的な目標に落とし込む
ゴールを日々の業務に落とし込むためには、具体的な目標やアクションプランを策定する必要があります。
以下のように、大きなゴールを実現可能な小さな目標に分解するのが効果的です。
| 短期目標(3ヶ月単位) | ・即効性のある改善策の実施・職員の意識改革・必要なツールや環境の整備 |
| 中期目標(6ヶ月~1年) | ・新システムの導入・業務プロセスの改善・職員のスキルアップ |
| 長期目標(1年以上) | ・組織文化の変革・新規事業の展開・施設・設備の改善 |
全員でゴールの意義を共有する
職員全体にゴールの重要性や背景を共有し、共感を得ることが成功のカギです。
定期的なミーティングや研修を活用します。
効果的な共有のためには、以下のような施策を実施しましょう。
| 共有手段 | 具体的な施策 |
| 定例ミーティング | ・週1回の全体朝礼・月1回のクラス別会議・四半期ごとの全体会議 |
| 視覚的ツール | ・目標達成ボードの設置・進捗状況のグラフ化・成功事例の写真掲示 |
| コミュニケーション機会 | ・小グループでのディスカッション・個別面談の実施・オンラインツールの活用 |
進捗を定期的に確認する
ゴールに向けた進捗状況を定期的にチェックし、必要に応じて改善策を講じます。
効果的な進捗管理のポイントは、以下のとおりです。
| 確認頻度 | 実施内容 |
| 週次 | ・クラスごとの達成状況確認・課題の早期発見・成功体験の共有 |
| 月次 | ・数値目標の達成度確認・改善策の検討・好事例の水平展開 |
| 四半期 | ・全体目標との整合性確認・次期計画の策定・成果の可視化と共有 |
柔軟に修正する
状況に応じてゴールやアクションプランを見直し、柔軟に対応することも重要です。
状況に応じた柔軟な対応のためには、以下のような取り組みが有効でしょう。
| 対応項目 | 具体的な取り組み |
| 定期的な見直し | ・月1回の進捗会議・四半期ごとの計画修正・年度途中での目標調整 |
| フィードバック収集 | ・職員からの意見聴取・保護者からの評価・子どもたちの反応 |
| 環境変化への対応 | ・社会情勢の変化・新制度への対応・地域ニーズの変化 |
外部機関と連携する
必要に応じてコンサルタントや行政機関と連携し、専門的なサポートを受けましょう。
効果的な外部連携のアプローチの例は、以下のとおりです。
| 連携先 | 具体的な取り組み |
| 専門家 | ・保育コンサルタント・ICTアドバイザー・労務管理専門家 |
| 行政機関 | ・補助金の活用・研修機会の確保・制度変更への対応 |
| 地域資源 | ・近隣施設との協力・地域企業との連携・ボランティアの受入れ |
ここで紹介したステップを着実に実行できれば、組織全体でゴールを共有し、一丸となって目標達成に向けて取り組むことが可能になるでしょう。
特に重要なのは、各ステップにおいて職員の意見を積極的に取り入れ、全員が当事者意識を持って参加できる環境を整えることです。
組織で同じゴールを共有することが保育園運営を成功させるカギ

変革は確かに勇気のいる挑戦ですが、組織と職員の成長には欠かせないプロセスです。
重要なのは、変革を通じて得られる価値を明確にし、ゴールに向かって全職員が一歩一歩着実に前進していくこと。
職員一人ひとりが目標に向けて主体的に行動し、組織全体の結束力を高めることが、子どもたちにより良い保育環境を提供し続けることができる、持続可能な組織づくりのカギになります。
もし、貴園がコーチングの導入を検討しているなら、当社が提供するコーチングプログラムをご活用ください。
私たちのサービスは、保育園の現場に特化したカスタマイズ可能なプランを提供し、職員一人ひとりの成長をサポートします。
専門のコーチが、保育園の組織文化に合った内容でコーチングセッションを実施するため、持続可能な効果をもたらします。詳細については、ぜひお問い合わせください。